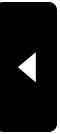2013年07月07日
会津のこと 八重の和歌
会津のことを書きたい、と云ったのは司馬遼太郎‥
わたしも会津のことが書きたいと、思い続けてきたのに、なかなか筆が進みませんでした。
NHK大河ドラマ『八重の桜』がとうとう会津若松戦争真っ最中ということで、ここで一気に書いてしまわないと、いつ書くの?というわけで‥いざ書かん。

・金戒光明寺・
京都守護職 会津藩が本陣とした、くろ谷 金戒光明寺。
今春、折しもNHK大河ドラマ「八重の桜」の放映に併せて、方丈の間で山本八重(新島八重)の自筆和歌や会津藩関連文書などが特別展示されていたのを見てきた時の話です。
後に新選組となる芹沢鴨、近藤勇、土方歳三が松平容保に拝謁した方丈には、常か今回だけかは分かりませんが、上段の間の奥に、松平容保書の軸が掛かっていました。
金戒光明寺は昭和9年の火災で御影堂や大方丈が焼失しているので、容保と近藤らが対面した大方丈は元の図面から再建されたもの。やはり当時のものでないとなると‥歳さんたちの息吹を感じとるのは難しい‥
案内係の人も、その辺りは気にされていたのか、“忠実な再建”を強調されていましたが。

特別展示場にもなっている座敷に入って真っ先に目についたのは、会津の旗印「會」。
10代の頃は、「誠」に比べてこの「會」が弱々しく見えたものです。
話はさらに遡りますが、高校の修学旅行が東北1コースと南九州2コースに分かれ、班ごとに好きな方を撰べました。絶対会津へ行きたかったわたしは、班のみんなを説き伏せ東北コース選択に成功。
まだ白虎隊ブームに沸く前の、素朴な“会津”の、空気感が懐かしく蘇りました。
明治の半ばに印刷された会津城下町図もありました。
藩士の屋敷などが詳細に書き込まれていて、日新館近くの山本覚馬の屋敷(お父さんの山本権八ではなかった)をはじめ、西郷頼母や神保修理、田中土佐など、八重の桜に登場する面々の屋敷の場所が記され、藩の施設や軍隊の解説なんかも細かく書いてあって、これは非常に興味深くおもしろかった。ルーペで隅々まで見たかったなあ。
もし会津で複製を出版してたら是非とも欲しい代物です。
明治中期の印刷ということは、会津が着せられた賊軍の汚名を晴らす歴史認識が、もうその頃にあったということなのでしょうか。
展示物の中で、観覧者の目をひいたのは、やっぱり新島八重の晩年の写真と自筆和歌の掛軸でした。
昭和3年(1928)に、黒谷の会津墓地で撮影された京都會津会の記念写真と、その節に寺を訪れた八重が書いた掛軸です。
「明日能夜は 何国の誰可 な可むら舞 な連し御城尓 残須月可計」
(明日の夜は 何国の誰か 眺むらん 慣れし御城に 残す月かげ)
「八十四歳 八重子」
この歌は、鶴が城を新政府軍に明け渡す前日に、八重が三の丸雑物庫の白壁にかんざしで彫り刻んだ一首と伝えられています。
八重はその後の人生で、この歌をことあるごとに書いたそうです。
この逸話は、銃を手に守り続けたわがお城を、明日は敵に渡さなければならない、その溢れ出る悔しさや切ない心情を城壁に刻みつける、勝ち気で烈しいハートの持ち主、八重の人物像を語り伝えていると思います。
そして、伝 松平容保筆の、白虎隊のことを詠んだ歌の掛軸も気になるものでした。‥つづく
わたしも会津のことが書きたいと、思い続けてきたのに、なかなか筆が進みませんでした。
NHK大河ドラマ『八重の桜』がとうとう会津若松戦争真っ最中ということで、ここで一気に書いてしまわないと、いつ書くの?というわけで‥いざ書かん。
・金戒光明寺・
京都守護職 会津藩が本陣とした、くろ谷 金戒光明寺。
今春、折しもNHK大河ドラマ「八重の桜」の放映に併せて、方丈の間で山本八重(新島八重)の自筆和歌や会津藩関連文書などが特別展示されていたのを見てきた時の話です。
後に新選組となる芹沢鴨、近藤勇、土方歳三が松平容保に拝謁した方丈には、常か今回だけかは分かりませんが、上段の間の奥に、松平容保書の軸が掛かっていました。
金戒光明寺は昭和9年の火災で御影堂や大方丈が焼失しているので、容保と近藤らが対面した大方丈は元の図面から再建されたもの。やはり当時のものでないとなると‥歳さんたちの息吹を感じとるのは難しい‥
案内係の人も、その辺りは気にされていたのか、“忠実な再建”を強調されていましたが。
特別展示場にもなっている座敷に入って真っ先に目についたのは、会津の旗印「會」。
10代の頃は、「誠」に比べてこの「會」が弱々しく見えたものです。
話はさらに遡りますが、高校の修学旅行が東北1コースと南九州2コースに分かれ、班ごとに好きな方を撰べました。絶対会津へ行きたかったわたしは、班のみんなを説き伏せ東北コース選択に成功。
まだ白虎隊ブームに沸く前の、素朴な“会津”の、空気感が懐かしく蘇りました。
明治の半ばに印刷された会津城下町図もありました。
藩士の屋敷などが詳細に書き込まれていて、日新館近くの山本覚馬の屋敷(お父さんの山本権八ではなかった)をはじめ、西郷頼母や神保修理、田中土佐など、八重の桜に登場する面々の屋敷の場所が記され、藩の施設や軍隊の解説なんかも細かく書いてあって、これは非常に興味深くおもしろかった。ルーペで隅々まで見たかったなあ。
もし会津で複製を出版してたら是非とも欲しい代物です。
明治中期の印刷ということは、会津が着せられた賊軍の汚名を晴らす歴史認識が、もうその頃にあったということなのでしょうか。
展示物の中で、観覧者の目をひいたのは、やっぱり新島八重の晩年の写真と自筆和歌の掛軸でした。
昭和3年(1928)に、黒谷の会津墓地で撮影された京都會津会の記念写真と、その節に寺を訪れた八重が書いた掛軸です。
「明日能夜は 何国の誰可 な可むら舞 な連し御城尓 残須月可計」
(明日の夜は 何国の誰か 眺むらん 慣れし御城に 残す月かげ)
「八十四歳 八重子」
この歌は、鶴が城を新政府軍に明け渡す前日に、八重が三の丸雑物庫の白壁にかんざしで彫り刻んだ一首と伝えられています。
八重はその後の人生で、この歌をことあるごとに書いたそうです。
この逸話は、銃を手に守り続けたわがお城を、明日は敵に渡さなければならない、その溢れ出る悔しさや切ない心情を城壁に刻みつける、勝ち気で烈しいハートの持ち主、八重の人物像を語り伝えていると思います。
そして、伝 松平容保筆の、白虎隊のことを詠んだ歌の掛軸も気になるものでした。‥つづく
Posted by sho惑星 at 22:46│Comments(0)
│かかる日のこと