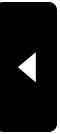2018年04月08日
幕末十一烈士
明治維新150年、と銘打った記念事業を目にしますが...新選組、京都守護職会津藩、奥羽列藩同盟等々にも肩入れしている身としては、戊辰150年、という言い方もしたいもの。
ところで、薩長土だけでなく、幕末の膳所藩も藩士による尊皇攘夷の思想と粛清の歴史がありました。
その事件で亡くなった藩士を、膳所十一烈士と呼んでいます。
思想的なことはさておき、十一烈士が遺したものが、ずっとずっと気になっていて...
それは、彼らが獄中で綴った和歌や漢詩。
いえいえ歌の内容ではありません。
墨も筆も与えてもらえなかったので、なんと紙撚(こより)や糸で描かれているのです!
江戸時代なので、楷書やなく草書やからねぇ、紐のようなもので文字の形を描こうとすれば、描けなくもないやろうけれど...
それにしてもあまりの器用さに、高校生だったわたしは唖然〜
紙撚文字といえば、平野国臣(ちょっとお気に入り〜西郷どんではどなたが演じられるのかなあ)のが有名で、もしかしたら幕末の頃の獄中で流行ってた!?
こんなに手間のかかることを平気でさせておく牢役人は人非人〜
墨筆を渡さない理由は何?
文字だけやなく、絵まで紙撚や糸で描かれていて...
ここまでくると、
獄中の手慰みを越えて、
これは趣味?
アート?
江戸時代の人に出来て、自分に出来ないわけがない、いつか自分も作ってみよう、と心に秘めておりました。
で、満を持して、ついにその時が...
大津市歴史博物館の企画展「膳所城と藩政」で、十一烈士の紙撚文字の短冊等も展示されるという。
図説大津の歴史に掲載されている写真を見ながら制作開始。
まあまあ似たものが出来ると軽く思っていたら、あにはからんや、とんでもない技術が必要なことに気づかされ...
何度も投げ出したくなるのを、えいっと我慢して、どうにかこうにか一首だけ作り終えました〜

増田正房の和歌より
膳所藩の企画展が始まって、初めて目にした実物の紙撚文字は、おそろしく精巧な出来で、これまた唖然〜
紙撚というより、毛筆の筆跡そのものといってもいいくらい。どのような工程で仕上げたのか、謎が謎呼ぶ...
もしかしたら、江戸時代の人はわたしたちより、超器用やったのかもしれへんな〜
そんな紙撚文字、糸文字も見られる展覧会は4月15日までです。
膳所の藩政を取りあげた大きな展覧会は初めてということで、西郷どんの薩摩島津家のような華やかさはあらへんけれど、膳所の歴史にも興味を持っていただけたら嬉しいです。

ついでに、5月13日〜26日に膳所城趾前の市民センター内の膳所歴史資料室にて、福山聖子絵画展を催します。
あ、紙撚で描いた絵画展じゃないので、お間違いのないよう(笑)
ところで、薩長土だけでなく、幕末の膳所藩も藩士による尊皇攘夷の思想と粛清の歴史がありました。
その事件で亡くなった藩士を、膳所十一烈士と呼んでいます。
思想的なことはさておき、十一烈士が遺したものが、ずっとずっと気になっていて...
それは、彼らが獄中で綴った和歌や漢詩。
いえいえ歌の内容ではありません。
墨も筆も与えてもらえなかったので、なんと紙撚(こより)や糸で描かれているのです!
江戸時代なので、楷書やなく草書やからねぇ、紐のようなもので文字の形を描こうとすれば、描けなくもないやろうけれど...
それにしてもあまりの器用さに、高校生だったわたしは唖然〜
紙撚文字といえば、平野国臣(ちょっとお気に入り〜西郷どんではどなたが演じられるのかなあ)のが有名で、もしかしたら幕末の頃の獄中で流行ってた!?
こんなに手間のかかることを平気でさせておく牢役人は人非人〜
墨筆を渡さない理由は何?
文字だけやなく、絵まで紙撚や糸で描かれていて...
ここまでくると、
獄中の手慰みを越えて、
これは趣味?
アート?
江戸時代の人に出来て、自分に出来ないわけがない、いつか自分も作ってみよう、と心に秘めておりました。
で、満を持して、ついにその時が...
大津市歴史博物館の企画展「膳所城と藩政」で、十一烈士の紙撚文字の短冊等も展示されるという。
図説大津の歴史に掲載されている写真を見ながら制作開始。
まあまあ似たものが出来ると軽く思っていたら、あにはからんや、とんでもない技術が必要なことに気づかされ...
何度も投げ出したくなるのを、えいっと我慢して、どうにかこうにか一首だけ作り終えました〜

増田正房の和歌より
膳所藩の企画展が始まって、初めて目にした実物の紙撚文字は、おそろしく精巧な出来で、これまた唖然〜
紙撚というより、毛筆の筆跡そのものといってもいいくらい。どのような工程で仕上げたのか、謎が謎呼ぶ...
もしかしたら、江戸時代の人はわたしたちより、超器用やったのかもしれへんな〜
そんな紙撚文字、糸文字も見られる展覧会は4月15日までです。
膳所の藩政を取りあげた大きな展覧会は初めてということで、西郷どんの薩摩島津家のような華やかさはあらへんけれど、膳所の歴史にも興味を持っていただけたら嬉しいです。

ついでに、5月13日〜26日に膳所城趾前の市民センター内の膳所歴史資料室にて、福山聖子絵画展を催します。
あ、紙撚で描いた絵画展じゃないので、お間違いのないよう(笑)
Posted by sho惑星 at 00:04│Comments(6)
│かかる日のこと
この記事へのコメント
この短冊と云うのか辞世を詠んだ句を見たことがあります。10年前ですからひと昔前に大津歴博の催しで、膳所ウオークがあり参加しました。膳所の町を歩いて石山方面に歩いていくと、本多神社の境内に膳所藩資料館がありそこで見せてもらいました。
筆で書かれたようでもないので聞いたら、獄中で出された飯を唾液でもって柔らかくして紙に貼りつけたとの説明がありました。ごはんでもって書かれた辞世の句すっごく印象に残っています。
当時のこと2007.11.12にこのウオークのこと4回に分けて記事にしていました。
そんなことよりもう10年も前のことなんですね。ショックですわ。
筆で書かれたようでもないので聞いたら、獄中で出された飯を唾液でもって柔らかくして紙に貼りつけたとの説明がありました。ごはんでもって書かれた辞世の句すっごく印象に残っています。
当時のこと2007.11.12にこのウオークのこと4回に分けて記事にしていました。
そんなことよりもう10年も前のことなんですね。ショックですわ。
Posted by 吉祥 at 2018年04月08日 07:56
ええっ! ご自分で作られたのですか、やっぱりプロは違いますね。
現物の写真も見にくいのに良くできているのでびっくりです。
最後のはねなどアレンジも入って素晴らしいです。
現物の写真も見にくいのに良くできているのでびっくりです。
最後のはねなどアレンジも入って素晴らしいです。
Posted by 爺爺の手習い at 2018年04月08日 21:33
at 2018年04月08日 21:33
 at 2018年04月08日 21:33
at 2018年04月08日 21:33こんにちは。
最初は意味がわからなくて
読み返して初めてわかりました。
こよりで文字を残(遺す)してあるのを
実践されたのですね。
しかも草書体で…。
やってみることに
すごいとしか言いようがありません。
書道展に行って
何が苦手かというと草書体です。
篆書は問題外ということで…。
最初は意味がわからなくて
読み返して初めてわかりました。
こよりで文字を残(遺す)してあるのを
実践されたのですね。
しかも草書体で…。
やってみることに
すごいとしか言いようがありません。
書道展に行って
何が苦手かというと草書体です。
篆書は問題外ということで…。
Posted by ぷーちゃん* at 2018年04月10日 15:16
at 2018年04月10日 15:16
 at 2018年04月10日 15:16
at 2018年04月10日 15:16to.吉祥さん
膳所藩資料館、まだ見たことがなくて...
紙撚文字も、本では知ってましたが、今回の歴博の展覧会で実物を初めて見ました。
色がついてるのは、何で着彩したのか、それもとても気になっています。
10年ひと昔と言いますが、ショックやなんておっしゃらずに(笑)
膳所藩資料館、まだ見たことがなくて...
紙撚文字も、本では知ってましたが、今回の歴博の展覧会で実物を初めて見ました。
色がついてるのは、何で着彩したのか、それもとても気になっています。
10年ひと昔と言いますが、ショックやなんておっしゃらずに(笑)
Posted by sho惑星 at 2018年04月11日 16:35
at 2018年04月11日 16:35
 at 2018年04月11日 16:35
at 2018年04月11日 16:35to.爺爺さん
よく出来ているように見えますが、ホンモノに比べたら歴然たる違いがありまして...
紙撚の材質が違うとは思うのですが、それにしてもどうやって作っていたのか?
再現してみると、見てるだけではわからなかった疑問も発見できて、それはそれで意義のあることだったなあ〜 というのが感想です。
もの作りが得意な爺爺さんも挑戦なさってはどうですか(笑)
よく出来ているように見えますが、ホンモノに比べたら歴然たる違いがありまして...
紙撚の材質が違うとは思うのですが、それにしてもどうやって作っていたのか?
再現してみると、見てるだけではわからなかった疑問も発見できて、それはそれで意義のあることだったなあ〜 というのが感想です。
もの作りが得意な爺爺さんも挑戦なさってはどうですか(笑)
Posted by sho惑星 at 2018年04月11日 16:43
at 2018年04月11日 16:43
 at 2018年04月11日 16:43
at 2018年04月11日 16:43to.ぷーちゃん*さん
もう、幕末やら歴史のことになると独りよがりな文になってしまいまして、ごめんなさい。
ぷーちゃん*さんは書をなさっておられるのですか?
わたしはまったくです...
草書も古文書も、ほぼ読めないまま、形だけそっくり真似て、この紙撚文字を作ってみました。
でも、こうやって作ってみると、筆順がわかって面白かったですよ♪
もう、幕末やら歴史のことになると独りよがりな文になってしまいまして、ごめんなさい。
ぷーちゃん*さんは書をなさっておられるのですか?
わたしはまったくです...
草書も古文書も、ほぼ読めないまま、形だけそっくり真似て、この紙撚文字を作ってみました。
でも、こうやって作ってみると、筆順がわかって面白かったですよ♪
Posted by sho惑星 at 2018年04月11日 17:07
at 2018年04月11日 17:07
 at 2018年04月11日 17:07
at 2018年04月11日 17:07